熊本日日新聞が報じた「熊本大病院教授が県内医師の診療従事を妨害か」という記事は、大学医局と地域医療の関係に潜む“見えない力学”を白日の下にさらしました。報道によれば、国立病院機構熊本医療センターで10年以上診療支援を続けてきた開業医に対し、熊本大病院神経精神科の教授が昨年1月「従事させないよう」要請し、大学の人権委員会はこれを「裁量権の範囲を逸脱したハラスメント」と認定したといいます。
大学医局は優秀な人材を育て、関連病院へ派遣することで地域医療を支えてきました。一方で、そのネットワークが“人事権”として機能し始めると、教授‐医局‐関連病院の三角関係は容易に力学的不均衡を生みます。記事が示す通り、教授の一存で外部医師の就労機会が奪われかねない状況は、まさに旧来型トップダウンの縮図です。
今回の件で特に憂慮すべきは、患者側の視点が置き去りになっている点です。精神科は未だ全国的にマンパワー不足が深刻で、10年超現場を支えてきた医師の突然の離脱は診療体制に直結します。それでも「教授の要請」が病院方針を揺さぶった事実は、組織の優先順位が患者ファーストより“貸し借りの論理”に傾き得ることを示唆しています。
一医師として自戒を込めて言えば、大学所属か開業かに関わらず、自らのキャリアを単一の組織に委ねきらない工夫が不可欠です。複数施設の非常勤で就労先を分散させる、法人化して契約主体を個人から切り離す──こうした選択肢が“医局の鶴の一声”から身を守るセーフティーネットになります。
同時に病院経営陣は、大学との良好な関係維持と患者利益のバランスを再考すべきです。人権委が「医学部教授の業務・権限との関連で合理性が肯定し難い」と断じた行為に追随すれば、組織としてコンプライアンスとブランドを同時に失いかねません。教授の懲戒は未定とのことですが、内部・外部の第三者機関が早期に結果を公表し、大学・病院双方が改善策を示すことが信頼回復への第一歩でしょう。
医局文化は功罪相半ばします。若手医師を指導し、過疎地に医師を送り込む善なる側面を生かしつつ、不透明な人事介入を防ぐルール作りが急務です。大学はガバナンス、病院は患者、そして私たち医師は専門職としての倫理──三位一体でチェック&バランスを機能させることでしか、今回のようなハラスメントを根絶する道はありません。今回の報道を機に、医療界全体が「権威よりも患者中心」という原点に立ち返ることを強く願います。

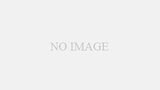
コメント