病院で働く医師にとって「オンコール」という言葉は日常語だが、その実態は外からはなかなか見えにくい。呼び出しが一度も来なかった日でさえ、携帯電話を握りしめながら過ごす緊張感は絶えず、真に休息したとは言いがたい。今回はオンコール勤務が抱える課題と、そこで感じる葛藤について紹介したい。
◆休まらない待機時間
オンコールは「呼ばれなければ自由」などと思われがちだ。しかし実際には、食事に出ても移動先で電話が鳴ればすぐに戻れる距離か、アルコールを口にしてよいか、子どもを風呂に入れても途中で抜けられるか――すべてを頭の中でシミュレーションしながら過ごす。精神的なスイッチは常に「業務モード」に半押しの状態だ。
◆手当という名の“ほぼボランティア”
多くの医療機関では、オンコールそのものに手当が付かないか、付いても微々たる額にとどまる。呼び出しに応じれば時間外手当は付くことが多いが、基本給の数割増程度である。交通費はつかない病院もある。家庭の時間や睡眠を削っても経済的報酬は乏しく、職務責任とのバランスが取れないという声が上がる。
◆少人数科では高頻度オンコール
常勤医師が少ない診療科では、オンコール当番は週に数回まわってくることもざら。年中オンコールという先生もいる。人数が少ないほど“負荷の集中”は加速度的に高まる。
◆即時コール文化のプレッシャー
総合病院によっては看護師のトリアージ段階で当該科のオンコール医師をコールする文化が根付いている場合がある。緊急事態ならそれでも良いと思うが、急ぎでない状況でも当直医に相談すらせず呼び出されることもある。オンコールの効率的な運用が望まれる。
◆持続可能な仕組みを目指して
オンコールは医療提供体制を支える重要なピースだが、医師の生活を圧迫し続ければ体制そのものが立ち行かなくなる。手当の適正化や院内プロトコルの明確化、遠隔診療ツールの導入による対応の選別――現場の声を基にした改革が必要だ。「呼ばれない夜」も医師にとっては立派な勤務時間であるという認識が、社会全体に広がることを願ってやまない。

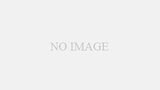
コメント