医師にとってコミュニケーション能力は必須——そう思い込んでいませんか?確かに、患者との信頼関係を築く上で会話は重要です。しかし、全ての診療科で同じレベルの対人スキルが求められるわけではありません。むしろ、「話すのが苦手」な医師でも高い専門性を発揮しやすい領域は存在します。
今回は、コミュニケーションが得意でない方にも適性があると感じる診療科をいくつか紹介します。
1. 病理診断科
「人と話すより、スライドと向き合いたい」という方に最も適しているのが病理診断科です。患者と直接会うことは基本的になく、組織標本を見て診断を下すのが主業務。顕微鏡の前で静かに自分の世界に没頭できる環境は、内向的な医師には理想的といえるでしょう。
ただし、カンファレンスや臨床医との連携、場合によっては説明責任もあるため、完全な「孤高の仕事」ではない点は注意です。
2. 放射線診断科
これも「しゃべらない仕事」の代表格です。CTやMRIの画像読影を行い、レポートを作成することが主な仕事。患者と直接対話することはほぼありません。読影の精度が問われる世界なので、ロジカルな思考と集中力を持つ医師にはうってつけです。
PACS(画像管理システム)と仲良くなれば、読影室の中だけで一日を終えることも可能。最近では在宅読影をする医師も増えており、対人ストレスを最小限にできます。
3. 麻酔科
「会話より手技が好き」なタイプにおすすめ。麻酔導入時には患者と簡単なやり取りがありますが、術中はバイタルとモニターと対話する時間がほとんどです。術前評価や術後説明もあるとはいえ、基本的には短時間のやり取りが中心。患者との深い関係性を築く必要が少ない分、精神的負担は軽めです。
ただし、外科医や看護師とのチーム連携は密なので、「完全に話さない」仕事ではありません。
4. 臨床検査科
基本領域19の中の一つに入っています。実態は正直よくわからないのですが、検査の手技、解釈などにフォーカスを置いた科であり患者対応は少ない分と思います。検査結果と向き合い、結果に基づいて思考する日々は、話すより考えるのが得意な医師にマッチします。病院によっては他科コンサルトがあるかもしれませんが、対話は理論的・限定的です。
「コミュ障=医師に不向き」は誤解
患者との会話が苦手でも、診断力や観察力、集中力といったスキルがあれば、医師として十分に活躍できます。実際、上記のような診療科では、口数が少なくても信頼される医師が多数います。
また、対話力は訓練で伸びる面もあります。診療科の選択と同時に、必要最小限のスキルを無理なく身につける工夫も大切です。
「自分は人付き合いが苦手だから医師に向いていない」と感じている方も、自分に合った診療科で、自分らしいキャリアを築ける可能性があります。選択肢は思っている以上に多いのです。

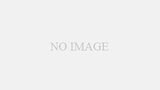
コメント